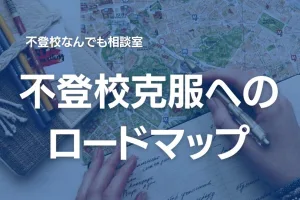【PR】この記事には広告を含む場合があります。
この記事でわかること
- 子どもが「学校に行きたくない」と言った時の対応法がわかる
- うまく対応できなかった場合でも、その後のフォローの仕方がわかる

子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、保護者は戸惑うでしょう。休むのを認めていいのか、無理に学校に行かせるべきか。子どもに付き添うためには仕事を休まざるを得ない。
いろいろなことを思うでしょうが、ここの対応がその後の不登校を大きく左右します。数か月・数年単位で悪影響を出さないために、保護者と指摘をつけるポイントをご紹介します。
初期対応のコツは正論と共感の使い分け
お子さんが「学校に行きたくない」と言ってきた場合、この時にどのように対応するかで、長期間不登校になるか、すぐに学校に登校するようになるかが変わってきます。
もちろん、すぐに学校に戻ることだけが答えではありません。例えば、クラスメイトからいじめがあるとか、教師からのハラスメントを受けている場合などは無理やり登校させることは危険です。場合によっては、自殺などにつながることもあります。
登校するかどうかという意味ではありません。お子さんとご家族の生活と気持ちを安定させるために初期対応が大事になるのです。
子どもの話に関する共感はとても大事です。一方で保護者として伝えなければいけないこともあるでしょう。
子どもの話は丁寧に聞き、保護者から伝えるべきはしっかり伝える。そのバランスをとることがとても重要です。
言葉は正論よりも共感重視
「学校に行きたくない」「休みたい」と保護者に行うまで、子どもなりにとても苦しんでいるはずです。
突然「学校に行きたくない」などと言ったら保護者が驚くことはわかっていますし、怒られるかもしれない。保護者の忙しそうな姿を見ていると、いつ話せばいいのかわからない場合もあるでしょう。保護者に言えずにしばらくの間は一人で我慢して無理やりに学校に行っていた子もいます。
しかし、子どもは自分の力だけではどうにもならず、勇気を振り絞って保護者に打ち明けてくれたのです。
その時に「忙しい時にそんなこと言わないで」とか「知らないわよ。自分で何とかしなさい」「そんなときは、△△すればいいでしょ!」などと言われたら、どうでしょうか。とても悲しい気持ちになり、ますます保護者に本音を話せなくなるでしょう。「親に心配をかけてはいけない」「『学校に行きたくない』なんて親に言ってはいけない」と思い、それ以降何も言ってくれないかもしれません。
【関連記事】
→ 毎朝の「学校に行く」「やっぱり行かない」の悩みを乗り越えるための3つのヒント
→ 親子の会話がなくて子どもの気持ちがわからない
あるいは、家族への不信感が高まり、のちのち「今、自分が学校にいけないのは、家族のせいだ」「一番つらい時に話を聞いてくれなかった」などと子どもが考えてしまうこともあります。
保護者の皆さんも仕事・家事・子育てに忙しい毎日を送っていて、ゆっくりお子さんの話を聞ける余裕はないかもしれません。いつも子どもの話をゆっくり聞くことは難しくても、子どもが「学校に行きたくない(行けない)」「学校を休みたい」などと言ってきたときは、必ず丁寧に話を聞いてあげましょう。この数時間のやり取りが、お子さんそしてご家族の人生を左右することになります。
例えば、どんなに大事な仕事をしていたとしても、職場が火事などの緊急事態になれば、仕事を一旦止めて逃げますよね。「火事より仕事が優先だ」という人はいないでしょう。
お子さんの「学校を休みたい」との訴えも火事と同じように何をさておいても、優先しなければならないほどの緊急事態なのです。
理由を確認
では、「学校に行きたくない」「休みたい」と言われたら、どのように対応すればいいのでしょうか。
まずは、本人が学校に行きたがらない理由を確認しましょう。「おなかの調子が悪い」「クラスメイトに嫌がらせをされている」「担任の先生が怖い」「よくわからないけれど行けない」などさまざまな答えが出てくると思います。
この中で、特に「よくわからない」という答えが非常に多いです。この場合、「いい加減なことを言うんじゃありません」「隠さないでハッキリ言いなさい」「理由がないなら学校に行きなさい」などと言うのは良くありません。なぜなら、本人が「よくわからない」というのは正直な答えだからです。実は、学校にいけない理由が「よくわからない」ことは非常の多いのです。
【関連記事】
→ 不登校の理由がわからないことが多い、聞き続けることがマイナスにも?経験者の意見から考える
本人のつらさを理解する
身体の具合が悪いのであれば、どこがどのように痛いのか。不安などであれば何が不安で、どんなことを考えてしまうかなどをじっくり聞いてみましょう。ここでも「そんなの大したことないよ」とか「気にしなければいい」などと正しそうな意見を伝えても意味がありません。
「それは苦しかったね」「それは大変だったね」などと本人の痛みや苦しみを理解していることをきちんと伝えましょう。
今まで本人なりに頑張ってきたことを認める
お子さんの努力を認めてねぎらってください。
先ほど説明したように、お子さんが「休みたい」とSOSを出すまで、家族に相談せずにしばらく一人で我慢していることがほとんどです。勇気を出して保護者に話してくれたことについても認めましょう。
あなたに話してくれたということは、お子さんはあなたのことを信頼しているのです。信頼されていることを誇りに思いながら、「信頼して相談してくれてありがとう」と感謝を伝えることも大切です。
対応方針は共感よりも正論重視
お子さんが学校を休む際の過ごし方や対応は、感情的にならず、冷静かつ論理的に対応することをお勧めします。
対応方針に関しては「わかる」だけではダメです。「わかること」より「できること」を重視しましょう。
お子さんに対しても「わからせよう」と説得ばかりするのではなく、「今できること」を増やしていくことが大事です。
【関連記事】
不登校対応のコツ:「わかること」より「できること」が重要
かならず理由に沿った対応を
先ほど紹介した通り、まずは「学校を休む(行かない/行けない)」理由の確認をすることが大事です。その時には、理由がわからない場合もあるので、それでも構いません。この時に無理に理由を聞き出そうとすると、理由を作り出してしまうことがあります。そうなると、問題解決はややこしくなります。
【関連記事】
不登校の「原因がわからない」ことも多い!その理由と対応策を徹底解説
初期対応あるある
私はこれまで20年以上不登校で悩むご家族のカウンセリングをしてきました。
その中で、多く見てきたパターンがあります。それは次のようなやり取りです。
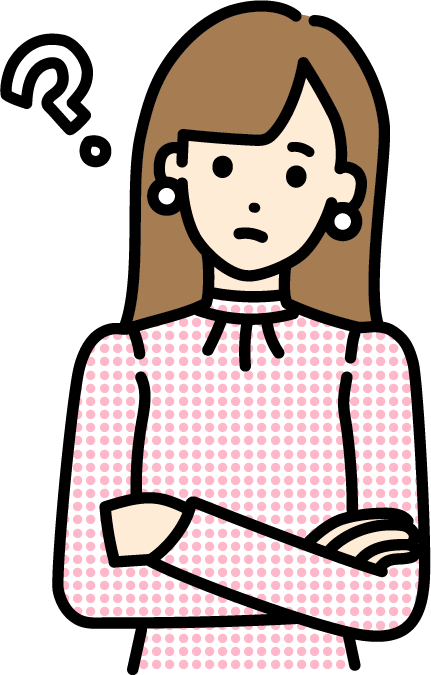
うちの子、最初は「頭が痛いから休みたい」って言ったので、その日は休ませて、家でゴロゴロさせたんです。
それで、学校休んで昼間からゲームしていて、次の日は大丈夫だろうと思ったら、また「頭が痛い」って。
それで次の日も休ませたんです。
そしたら9時ごろになったら、ケロッとして、ゲームをしはじめて。夜遅くまでゲームをやって。朝寝坊するようになって。
それが、しばらく続いて、いつからか朝「頭が痛い」ということもなく、当たり前のように昼頃に起きてきて夜中までゲームをやるようになってしまいました。
最近は、ゲームのやりすぎだからゲームを取り上げようとしたら、暴れ始めて「学校にいけないのはお前たちのせいだ」「死んでやる」などと言い出すので、どうしたらよいのか困っています。
このようなご家庭からの相談がとても多いです。
私たちのカウンセリングでは、このような状況で数か月から数年過ごしてきた、ご家族からご相談を受けて、数か月かけて問題解決を図っております。
しかし、理想は、このような状況になる前に対応することです。そこで、今回は初期対応について考えていきましょう。
【関連記事】
毎朝の「学校に行く」「やっぱり行かない」の悩みを乗り越えるための3つのヒント
体調不良が理由の場合
本人が体調不良を訴えている場合、体調不良の文脈に沿った対応が必要です。先ほどの例では「頭が痛い」と本人が訴えているにも関わらず、昼間本人の好きなように過ごしていました。体調不良であれば、一日中安静に過ごすことが有効でしょう。昼間もできるだけ横になって、ゆっくり眠る。ゲームもやらない。やるとしても例えば学校に行っている日と同じ時間だけ認めるのがよいでしょう。もちろん、必要に応じて病院を受診することもおすすめします。
【関連記事】
→ 不登校と起立性調節障害 特徴から改善方法やカウンセリングまで徹底解説
→ 【不登校の背景】過敏性腸症候群(IBS)症状・原因・対策を解説
体調不良以外が理由あるいは不明の場合
体調不良以外の理由、例えば「クラスメイトに嫌がらせをされた」「担任の先生が怖い」「部活動で嫌なことがあった」などの場合は、安静にしたところで良くなりません。なので、安静にする必要はありませんが、体調不良ではないので勉強や食事はできるはずです。
「休んで家にいるなら、○○だけはやってほしい」と勉強や手伝いなどを提案することをおすすめします。散歩や筋トレも効果的ですね。
体調不良以外の場合は、対人関係などなんらかの悩みや不安を抱えています。そのため、夜いろいろ考えてしまい眠れなくなり、朝起きれないという悪循環が起きることがあります。
運動をすることで体をほどよく疲れさせることができ、午前中に日光を浴びることで体内時計を整えることで睡眠の量も質も安定します。
【関連記事】
不登校の昼間の過ごし方はどうすればいい?スクールカウンセラーが解説
まずはゆるい目標設定で
「他人から『○○しなさい』と人から言われると、やる気をなくし、『××するな』と言われるとしたくなる」のが、人間の心理です。
「見るな」と言われると見たくなりますし、「宿題しなさい」と言われるとそれまでやる気があった場合でもやる気をなくしてしまう経験ありませんか?
このように、「ゲームをするな」と言えば、ゲームのことが気になってしまいますし、「勉強をしろ」と言われると勉強する気が無くなってしまいます。皆さんも一度や二度は似たような経験をしているでしょう。
「学校を休むのだから、6時間分の勉強をしなさい」などと提案するのはよくありません。
私たち大人でも「今日は仕事休んでいるけれど、6時間△△をしなさい」と言われたら、どんなに楽しいことでも続けるのは難しいものです。勉強や手伝いや運動を提案する場合は、最初はとても簡単な設定をしましょう。
子どもに「えー、少なすぎるよ。もっとやりたい」と思わせたら最高ですね。
筋トレと同じく、簡単なことから始めつつ、徐々に負荷をかけていくのです。
例えば、初日は1問だけ解いて、2日目には2問、3日目には3問と負荷をかけていけば、1か月後には1日30問に取り組むようになります。
初日から30問をむりやりやらせるよりも、簡単で成功する確率が非常に高まります。
「もっとやりたい!」と言われた場合も「じゃあ、6時間勉強しよう」などと突然高い目標を設定してはいけません。
「そう?じゃあ、もしまた休む時は今日よりも少し増やそう」などと徐々に増やしていくことが大事です。
あくまでも、お子さんが「これなら大丈夫。保護者は私のことをちゃんと考えてくれている」と思ってもらうのです。
プラン通りいかないことも想定内
ここまで、学校を休む際の対応について、聞き取り方や対応策などについて、紹介してきました。
さまざまなご家庭がある中でこれらの対応が難しい、あるいは対応したけれどうまくいかない、そんなご家庭も多いでしょう。
特に共働きやひとり親家庭などでは子どもと話す時間もなく、昼間ずっと子どものそばにいるわけにもいきません。その結果、「ちゃんと昼間勉強するって言ったけれど、結局ゲームばっかりしてたみたいで、そのことを注意したら、部屋に閉じこもってしまった」ということもあります。
また、「昨日は張り切って勉強していたのに、今日は全然勉強しない」などと言うこともあります。
「絶対にうまくいく」と考えるのではなく「うまくいかなくても何とかなる」と考えて柔軟に対応することが大事でしょう。「何にもしない」もしくは「口うるさくガミガミ言う」のどちらかといった極端な対応はよくありません。「ちょっとここを工夫してみようかな」「ダメ元であれを試してみようかな」といろいろ考えることが大事です。
もちろん、ご家族だけで考えることには限界があると思いますので、担任の先生やスクールカウンセラーをはじめとした他の人の意見も参考にすると良いでしょう。
【関連記事】
【不登校の相談先①】スクールカウンセリング
初期のポイントを抑えることでその後が大きく変わる
子どもが「学校を休みたい(行きたくない/行けない)」と言ってきた場合、話してくれたことに関して感謝を伝えること。そして、理由を確認して、理由に沿った対応をすることが大事であると説明してきました。
初期対応でどれだけ家族が試行錯誤したかによって、その後の生活が大きく異なります。数日欠席しただけで通常登校を再開する子もいますし、欠席が長引いた場合でも家族も子どもも「どのように過ごせばいいのか」「今何をすればいいのか」などがわかるので、将来に対する不安などが減ります。そして、何より家族関係が良好になります。
【関連記事】
毎朝の「学校に行く」「やっぱり行かない」の悩みを乗り越えるための3つのヒント
不登校のゴールは再登校ではなく子どもの自立(自律)
ご家族にはご家族の仕事や都合があるでしょうが、「学校を休みたい(行きたくない/行けない)」と子どもが言った時にしっかり対応することで、その後の家族の負担は減ります。
より良い家族関係のために、このページが参考になれば幸いです。
不登校克服のロードマップ へもどる

投稿者プロフィール

最新の投稿
 不登校なんでも相談室2024年4月24日友達とのSNSトラブル:原因、影響、そして解決策
不登校なんでも相談室2024年4月24日友達とのSNSトラブル:原因、影響、そして解決策 不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校の原因はなに?7つの要因と1つの謎を解説
不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校の原因はなに?7つの要因と1つの謎を解説 不登校なんでも相談室2024年4月24日教室には入りたくないけれど、部活には行きたい
不登校なんでも相談室2024年4月24日教室には入りたくないけれど、部活には行きたい 不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校と昼夜逆転:子どもの生活リズムを整えるためのヒント
不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校と昼夜逆転:子どもの生活リズムを整えるためのヒント