【PR】この記事には広告を含む場合があります。

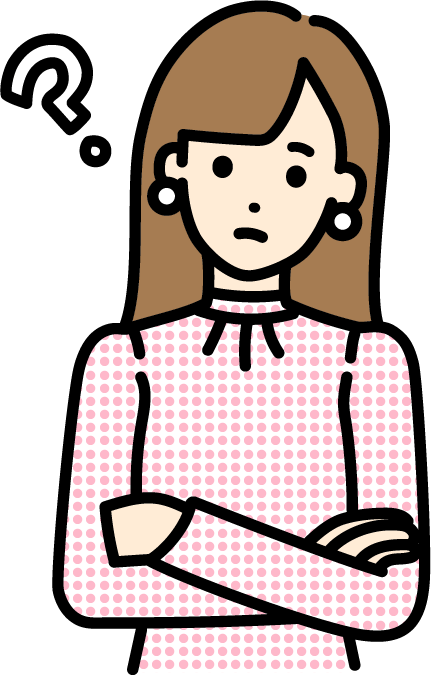
子どもが学校に行かないことについて、欠席連絡をするのが苦痛。毎日担任の先生から連絡があるのも、正直辛い。

子どもが、「担任の先生が怖い」といって学校に行かない。担任にそのまま伝えるわけにいかないしどうしよう。

このような悩みを持っているご家族は多くいらっしゃいます。
本記事では、担任との関係について解説していきます。
学校は本来、とても有意義な場所です。勉強はもちろん、体力づくりもできますし、人間関係を学ぶこともできます。しかし、中には担任の先生との関係がうまくいかずに、学校に行きたくなくなってしまったこどもも少なくないようです。文部科学省の資料によると、学校に行きたくない理由の3割が「学校の先生」だとされています。ここでは学校の先生の中で一番子どもたちと接する機会が多い、担任の先生に関して取り上げます。
学校の教員にもいろいろな人がいるのは当然
文部科学省の学校基本調査によると、学校の教員の数は以下の通りです。
| 校種 | 教員数 |
| 小学校 | 41万6833人 |
| 中学校 | 24万8694人 |
| 高等学校 | 25万1408人 |
小学校の教員は41万人以上、中学校・高等学校でも25万人前後います。小中高校の教員を合計すると約91万7000人です。

都道府県の総人口ランキングによると、第40位の和歌山県全体の人口が92万人超なので、およそ教員を全員集めると和歌山県の人口とほぼ同じになります。
それだけ人数が多ければ、優しい人がいれば、怖い人もいます。相性の良い人もいれば、どうしても好きになれない人もいるのが当然です。。
皆さんが子どもの頃を思い出してください、みなさんの学校の中に、勉強の成績がいいけれどトラブルが多い生徒、成績は良くないけれど人気者、体育がとても上手な生徒などいろいろなタイプの子どもがいませんでしたか?
隣の席に座るのが好きな人の場合もあれば、苦手な人の場合もあるでしょう。教員も91万人以上いれば、いろいろな人がいるのは仕方がないことです。
特に近年は、教員不足が深刻化しています。その結果、教員採用試験の倍率が低下し、10年以上前なら採用されなかったであろう志願者が採用されることもあります。その結果、スキルの低いにもかかわらず教員として担任を持たざるを得ない場合も出てきます。
その中で、尊敬でき頼りがいのある教師が担任になればいいですが、頼りにならない教師に当たってしまうこともあります。その結果、担任との関係が悪く、不登校になってしまう場合もあるのです。
担任との関係が不登校のきっかけに
担任の先生との関係で不登校になる場合、実際には以下の3つの理由が考えられます。
ハラスメントがある
以下は、子ども向けではなく社会人の職場のハラスメントに関する6分類です。この6種類を学校の教師と子どもに当てはめて考えるとわかりやすいです。
身体的な攻撃(暴行・傷害)
いわゆる体罰といわれるものですね。殴る、蹴る、モノを投げつける、首を絞める、つねる、叩く、などです。
精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
教師にとっては冗談のつもりで行った言葉でも、子どもにとってはとても傷つくことがあります。
例えば、クラスの他の子に対して「こんなこともできないと、Aさんのようになってしまいますよ」といった言葉かけなどは、Aさんにとって侮辱でしょう。
人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
昔は廊下に立たせるといったことがありました。あるいは、無視ではなくても、他の子の質問には丁寧に答えるのに、特定の子の質問には答えなかったり、えこひいきなどです。
過大な要求
例えば宿題をたくさん与えるとか、忘れ物があったからといって厳しいペナルティを与えるとか、テストで間違えた漢字をノート何ページにもわたり書き直すことを強制したり、「それは、やりすぎだろう」と思うことがこれに当たります。
過小な要求
教師の方で勝手に制限をすることがあります。もちろん、子どもや保護者から依頼があったり、子どもが納得した上で制限をすることは悪いことではありません。合理的配慮としてむしろ良いことだと思います。一方で「この子にはやらせたくない」「この子はできないに決まっている」という教師の思い込みから、特定の子にだけやらせないということは危険です。
個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
家庭環境や家族のことについて、意味もなく質問をしてきたり、他の教師や子どもに話したりすることで、子どものプライバシーを侵害していることがあります。
以上は、パワーハラスメントの6分類を元にしたハラスメントの紹介でした。この6分類は職場のパワーハラスメントに関する考え方なので、学校では少し違うところがあります。しかし、参考として、先生からのされた嫌なことが何に当てはまるのかを考えておくといいでしょう。
また、きれいに6分類できるわけではなく、なかには複数の項目にあてはまることもあります
例えば、給食を食べきれずに、給食の時間が終わっても食べさせる行為は私たちが子どもの頃はよくありました。
最近でもたびたびニュースになります。そのように給食の時間が終わっても食べさせるという行為は、
「一人だけ残されて恥ずかしい」…(2)精神的攻撃
「休み時間で他の子が遊んでいるのに遊ばせてもらえない」…(3)人間関係からの切り離し
「食べられないものを無理に食べさせる」…(4)過大な要求
…といった複数の項目に該当する場合などがあります。
担任に対して不信感がある
先生に何か相談事をした時に、誠実に対応してくれなかったと感じた経験があると、それがきっかけで先生や学校に対して不信感を持つ場合があります。
学級には30人以上の子どもがいるため、どんなに気を付けていても平等に対応はできません。担任の先生がクラスの児童・生徒全員に同じ回数の声掛けをして、同じ長さで関わって、同じ内容の話をするのは不可能です。一人に1分ずつ声をかけたとしても30分かかってしまいます。授業はもちろん事前の準備や職員会議などもありますので、一人に1分ずつ声をかけるのも無理でしょう。
「あの子にばかり声をかける」「私のことは心配してくれない」など、児童・生徒、そして保護者にとっては不公平を感じることがあります。子ども同士のトラブルがあった時も同様に、トラブルに関わった子全員に全く同じ話をして、全く同じ時間関わることは無理です。さらにそのトラブルを目撃したとしても、経緯を全て把握できるわけではありません。まして、目撃してないで子どもの訴えを聞いてトラブルを把握した場合は、客観的で正しい判断が出来ないこともあります。
その結果「担任がえこひいきしている」などと感じて、担任不信につながることがあります。先生を信頼できないと、授業にも身が入らず、だんだん学校に行くことが苦痛になってしまいます。
繰り返しになりますが、何人の先生が30人以上のクラスで全員に平等に声をかけることは難しく、クラス全員の動きや人間関係を把握するのは困難です。そして、そもそも91万人もいる先生の中には、力のある先生もいる反面、頼りにならない先生もいる。これは仕方のないことなのです。
「仕方がないからあきらめろ」というつもりはありません。「学校に過度な期待をせずに、子どものことは家族が守っていかなければいけない」のです。
担任の存在自体が怖い
ハラスメントとまでいかなくても、担任の先生が注意する時の口調や言葉が怖くて、学校に行くのが嫌になってしまう場合があります。他の生徒が怒られているのを見るだけでも、自分が怒られているような気持ちになって気が休まりません。怒鳴ったり一方的に怒る先生が担任だと、毎日ビクビクしてしまいますよね。
一方で、担任の先生の乱暴な言動がなくても、特に異性の先生の場合は、子どもが怖いと思う場合が多いようです。確かに、子どもにとって今まで会ったことのないタイプの大人だと、恐怖や不安を抱くことは考えられます。私たち大人でも、人事異動などで直属の上司が今までと違うタイプの人物になったら、「やりにくいなぁ」「苦手だなぁ」と思うことはありますよね。子どもならなおさらです。
そのような状況で、家族から「新しい担任の先生どう?」などと聞かれると「なんだか怖い」などと答えるでしょう。本人に不安が強かったり、家族が不安が強いと「なんだか怖い」から、恐怖や不安が膨れ上がってしまうこともあります。
理由はなくなんとなく怖い場合、いわゆる相性の問題であり、上記のハラスメントとは違い、担任側に問題がない場合も多くあります。したがって、子どもが「先生を怖がっている」ということで、学校にクレームを言ったり、担任変更を訴えるのは適切ではありません。子どもを守ろうという思いなどから、学校に要望をしたくなる気持ちはわかりますが、慎重な対応が求められます。
【関連記事】
【不登校の理由がわからない】過剰な原因追及は危険 オウム返しと記憶の汚染から考える
担任や学校への働きかけよりも、子どもの恐怖心や不安の高さに焦点を当てた対応が求められる場合もあります
対策について
担任の先生への恐怖について実際にハラスメントを受けている場合と、なんとなく相性が悪い場合があることをお伝えしました。
次に対策について学校側、保護者側、子ども側の3つの視点でみていきます。その上で、もし学校を休む必要がある場合の注意点もお伝えいたします。
学校に期待できること
ハラスメントがあった場合、学校側は該当する教員への指導ができます。まずは率直に管理職やスクールカウンセラーに相談するのが良いでしょう。
また、先生との関係が原因で不登校になった子どもの場合、まずは担任の先生の家庭訪問や子どもへのコンタクトを避けた方が良い場合もあります。この場合も、管理職やスクールカウンセラーに相談することをおすすめします。
【関連記事】
【不登校の相談先①】スクールカウンセリング
保護者ができること
保護者ができることについて、子どもへの対応と担任への対応に分けて考える必要があります。具体的に見ていきましょう。
担任不信を抱いている子どもへの対応
まず、子どもが担任に関する恐れや不満などを訴えてきた場合は、しっかりと聞いて本人の辛さを理解しましょう。
大事なのはジャッジはしないこと。「それは担任の先生が悪い」とか「担任の先生にそんなことを言われるあなたが悪い」などと、すぐに判断せず、まずは状況確認をしましょう。判断をするのは担任の先生からも話を聞いた後です。お子さんの辛い状況を聞くとついつい感情的になるでしょうが、出来るだけ落ち着きましょう。「うちの子が正しくて、担任が間違っている」「あの先生がそんなことをするはずがない」「うちの子が悪いのかもしれない」などと先入観を持たないことが大事です。
特に子ども同士のトラブルに対する担任の対応については、子どもからの話と実際が大きく違うことがあります。この場合、子どもの話だけで動くのは危険です。しっかりと教師からも説明を聞き、疑問点や食い違いなどがあれば、確認していきましょう。
子どもとの会話が少ない場合は、まずは会話を増やすことが大事です。
【関連記事】
親子の会話がないため子どもが何を考えているかわからない
【不登校の理由がわからない】過剰な原因追及は危険 オウム返しと記憶の汚染から考える
担任への対応
先生と直接話し合う必要がある場合は、話し合いの目的は「子どものために先生方とどのような連携をとっていくか」にしましょう。これまでの対応について糾弾したり、こちらの要求ばかりを伝えてもうまくいきません。担任の先生を子育てのパートナーと考えて穏やかに意見交換をできるといいですね。
もちろん、不信感があったり、顔も合わせたくないということもあるでしょう。その場合は、養護教諭や管理職など、自分にとって比較的話やすい学校関係者にまず相談しましょう。
マナーを忘れないことも大切です。例えば、先生へ連絡を取るときに保護者が時間に余裕がある夜遅くや休日に連絡をすることはやめましょう。他にも長々とクレームを言い続けたり、暴言を吐いたり、土下座を強要するようなことは避けるべきです。
学校側に問題があり、保護者の訴えがもっともな場合でも、丁寧な言葉遣いが必要です。子どもを守ろうとして学校に行ったものの、乱暴な言動のために保護者側が警察に逮捕されてしまう事件も実際に起きています。そのようなことになっては、保護者自身はもちろん、お子さんにもマイナスの影響が出てしまいます。
特に担任の感情的な言動などを改めてもらいたい場合などは、こちらまで感情的になるのではなく、冷静に対応する必要があります。感情的にならなくても話ができることを示しましょう。
学校に相談しにくい場合
学校の中に相談する人が見つからない場合は教育委員会に連絡することもできます。この際に気を付けることは、最初から「担任が信用できないから変えてほしい」などと“最初から要求しない”ようにしましょう。問題が複雑になりますし、モンスターペアレント扱いされるとうまくいきません。
まずは「学校に相談したいのだけれど相談しにくい」ということを相談してみましょう。
何かの要求を出すのではなく、まずは相談をするというスタンスが大事です。
感情的に言うと恫喝しているように思われてしまいます。理詰めで丁寧に言った方が教育委員会の協力も得やすいです。
学校や教育委員会に対して不信感があり、相談しにくい場合は、まずは民間のカウンセラーに相談して作戦会議をすることが有効です。
カウンセリングと言っても、気持ちを整理したり自分自身の内面に関して話す必要はありません。家族の将来について一緒に考えることもできます。

こどものみなさんへ
【先生とのことでこまっている、こどものみなさんへ】
学校に行きたくない理由が先生だとしても、どうかひとりだけでは悩まないでください。
勇気を出してご家族に相談するのはとても良い方法です。
ご家族は、あなたのために、いい方法を見つけてくれるでしょう。
もし、どうしても「担任の先生とあわない」「一緒にいたくない」という時は、学校を休むことも大事です。
しかし、どんなに努力をしても、すぐによくならないかもしれません。
苦手な先生が担任の場合、本当にストレスが溜まりますよね。それでも、自分のことばづかいなどには気をつけましょう。
苦手な人やイヤな相手だとしても、キズつけるような言葉やあばれたりすることは、やめましょう。
休む際の注意点
お子さんが担任の先生とうまくいかない場合。特にハラスメントを受けている場合は、学校を休むことも選択肢になります。その際の注意点として、家での過ごし方です。
「学校を休むこと」と「家でダラダラ過ごすこと」は違います。家庭での勉強をしっかり続けるようにしたいですね。
担任が苦手なのであれば、学年が変わり新しい担任になった時に再登校できることが多いです。実際に、新年度から学校に休まず登校できるケースをたくさん見てきました。
一方で、休んだ時に家でずっとゲームをしていたり、夜更かしをしたり、勉強をしないでいると、「勉強がわからない」とか「授業がつまらない」という別の理由が出来てしまい、学校に戻りにくくなります。ゲーム依存、昼夜逆転、勉強について行けないことなどが不登校の要因になってしまうからです。
また、学校に行けなくても家庭での学習をしっかりしていれば、出席扱いになることもあります。
学校を休む際に家での過ごし方を家族と子ども自身で共有しておくことが大事です。
【関連記事】
子どもに「学校に行きたくない」と言われたときの対応。正論と共感の使い分けが大切
不登校のゴールは再登校ではなく子どもの自立(自律)
不登校の昼間の過ごし方はどうすればいい?スクールカウンセラーが解説
不登校の休日の過ごし方は、出来るだけ楽しもう!
担任とうまくいかなくて不登校になった場合
この記事では、不登校の原因が学校の先生との関係にある場合にどうすればよいか、取り上げました。
子どもにとって、起きている間の半分以上が学校で過ごしている場合が多く、その意味で学校は子どもの生活の場の中心といえます。そんな大事な場である学校なのに、教師の言動のせいで学校に行きたくなくなってしまうのは、本当に残念ですよね。
こどもたちがストレスなく学校生活を楽しめるように、学校、保護者、そしてこども自身ができる限りのことをしていきましょう。

文献
都道府県人口ランキング
https://www.mext.go.jp/content/20211006-mxt_jidou02-000018318-2.pdf
https://for-teachers.manalink.jp/useful/trouble/teacher/159myng5c
不登校克服のロードマップに戻る
投稿者プロフィール

最新の投稿
 不登校なんでも相談室2024年4月13日子どもの自己肯定感を高めるための親のアプローチ
不登校なんでも相談室2024年4月13日子どもの自己肯定感を高めるための親のアプローチ 不登校なんでも相談室2024年4月12日中学生活のスタートに立ち向かう:中1ギャップとその克服法
不登校なんでも相談室2024年4月12日中学生活のスタートに立ち向かう:中1ギャップとその克服法 不登校なんでも相談室2024年4月5日小学校デビューの壁、小1プロブレムに注意!
不登校なんでも相談室2024年4月5日小学校デビューの壁、小1プロブレムに注意! 不登校なんでも相談室2024年3月31日不登校で朝起きられないのは、なまけ? 原因と解決策を解説
不登校なんでも相談室2024年3月31日不登校で朝起きられないのは、なまけ? 原因と解決策を解説







