【PR】この記事には広告を含む場合があります。
この記事でわかること
- 場面緘黙がどういう状況なのかがわかる
- 場面緘黙になることが、本人のワガママや保護者の育て方の問題でないことがわかる
- 場面緘黙の子にどのような対応をすればよいかがわかる
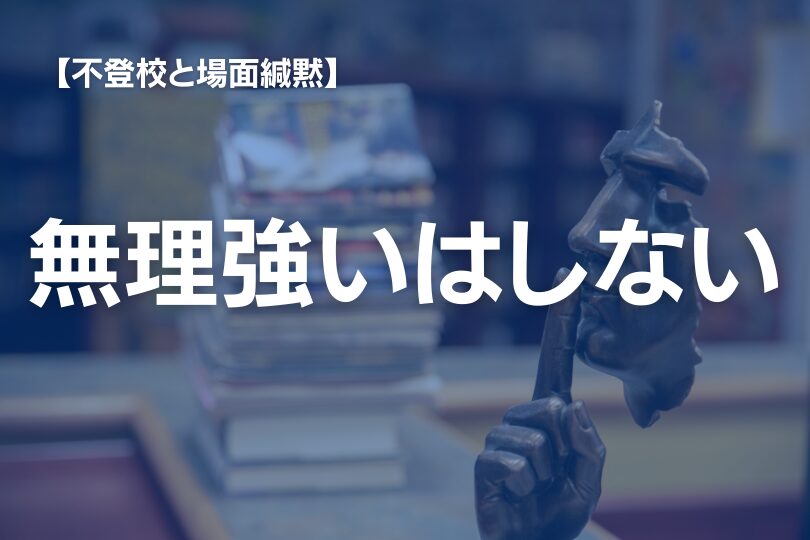
「場面緘黙」とは、ある場面では話すことができるのに、別の場面では話せなくなる症状のことです。
この記事では、場面緘黙に悩むお子さんたちをサポートする方法や対応を解説しています。
緘黙とは?
緘黙(かんもく)とは、ある場面では話せるけれど、別の場面では話せなくなる症状(場面緘黙)です。
不安障害の一種とされていて、多くは家庭以外や学校で話すことが出来ません。
大人でも緘黙はありますが、大抵は幼い時に発症する場合が多いようです。
例えば、幼稚園や小学校に新しく入った時、転校した時に、人前で注目されながら話すことにとても不安を覚えて、話せなくなってしまうのです。
一旦話せなくなると、次に話すとみんなからなんて言われるんだろう。と気になって、ますます話すことができなくなってしまいます。
場面緘黙のお子さんの場合、多くは家庭で話せて学校では話すことができません。
そのため、学校に行っても授業で発表ができなかったり、休み時間に友達と遊ぶこともできず、先生との会話も難しいため、不登校になることもあります。
原因は?
原因はひとつではなく、いろいろな要素が組み合わさって、場面緘黙になると言われています。
この記事では代表的な3つの要因をご紹介します。
行動抑制的な気質
脳の扁桃体が反応しやすいと、いろいろな刺激に過敏に反応します。
そのため、家の中では不安になることが少ないのでリラックスしていますが、家の外に出ると緊張してしまって話せなくなってしまいます。
環境の変化
慣れ親しんだ環境から新しい環境に変化したときに、大きなストレスを感じます。繊細なこどもは新しい学校や、新しいともだちに馴染むのに時間がかかるので、そうしたことがきっかけで話せなくなってしまう場合もあります。
発達障害との関係
ことばを理解するのがなかなか苦手なこどももいます。それで、家族の中ではよくしゃべりますが、より複雑で難しい会話をしないといけない学校では、話せなくなってしまう場合もあります。
【関連記事】
→ おちつきがない・集中できない・忘れ物をする:ADHD(注意欠陥多動症)
→ 聞く、話す、読む、書く、計算、推論のいずれかが著しく困難:LD Learning Disability(学習障害)
→ 【不登校と発達障害】ASDについて特徴や改善法などを徹底解説
よくある誤解

学校で話せないけど、家では元気に話せているし。たんなるワガママなのでは?
学校でも我慢すれば話せるようになるかも。

話せる場面と話せない場面があること自体が「場面緘黙」の特徴です。わがままでもないですし、無理に話させるのはおすすめしません。
不安の少ない家庭ではよく話すのに、学校では話せないので、単なるワガママだと思われる時もありますが、話せる場面と話せない場面があること自体が「場面緘黙」の特徴です。
ワガママではなく、話したくても話せないんだということを理解してあげることが大切です。
親の育て方が過保護、または厳しすぎるから話せないんだというのも、大きな誤解です。
緘黙に悩んでいる本人は、とてもおとなしい性格をしていて、周りの変化に敏感です。
学校でも問題行動はないので、先生から「学校で全然話さないんです」と言われて初めて分かったというケースもあります。
緘黙のある子どもの親と、緘黙のない子どもの親には違いがないことが立証されているので、育て方に問題があるという説は撤回されています。
緘黙に悩むこどもたちをどうサポートできるか
学校や他の人の前で話せないこどもは、「話さない」のではなく、「話したくても話せない」ということを、周りはよく覚えておく必要があります。
できないことを無理にさせられたら、誰でもストレスですよね。そこで、話さないことを責めたり、話すよう強要するのはやめましょう。
緘黙についてよく知らないので、良かれと思って話すよう無理強いしてしまう先生もいます。なので、親は「緘黙」について先生とよく話し合っておくと、学校を安心できる場所にしてあげられるでしょう。
書くことでコミュニケーションできるようなら、筆談したり、話さなくても遊べる方法を試したり、いろいろ工夫できるかもしれません。
さいごに
話したくても、緊張して話せなくなってしまう症状「緘黙」についてご紹介しました。
誤解されやすい症状なので、なかなか相談できずに、長い間悩んでおられるかもしれません。
緘黙について正しい知識が広がれば、もっとみんなが安心して、いきいきとした毎日が送れるようになりますよね。
それで、ひとりで悩まず、ぜひ専門機関に相談してみてください。

引用文献
https://h-navi.jp/column/article/35026386
https://mutism.jp/about-sm/
不登校克服のロードマップ へもどる
投稿者プロフィール

最新の投稿
 不登校なんでも相談室2024年4月24日友達とのSNSトラブル:原因、影響、そして解決策
不登校なんでも相談室2024年4月24日友達とのSNSトラブル:原因、影響、そして解決策 不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校の原因はなに?7つの要因と1つの謎を解説
不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校の原因はなに?7つの要因と1つの謎を解説 不登校なんでも相談室2024年4月24日教室には入りたくないけれど、部活には行きたい
不登校なんでも相談室2024年4月24日教室には入りたくないけれど、部活には行きたい 不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校と昼夜逆転:子どもの生活リズムを整えるためのヒント
不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校と昼夜逆転:子どもの生活リズムを整えるためのヒント







